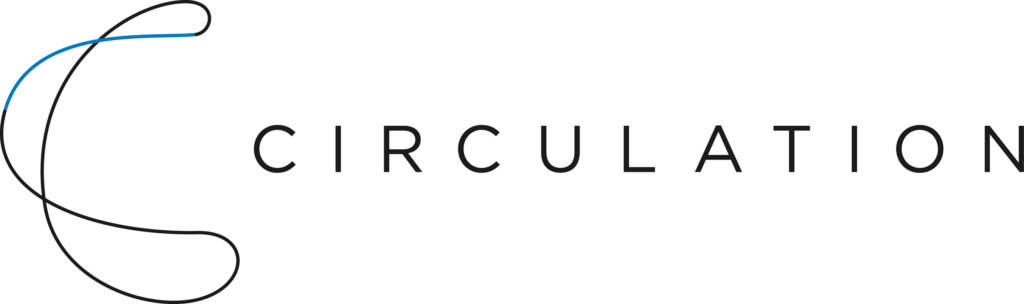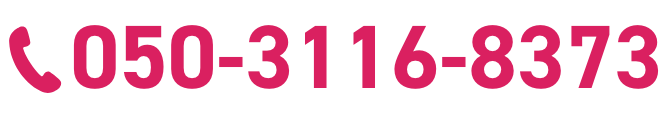多い日で1日に150件の問い合わせ。プロ人材のニーズに合わせ、リアルタイム・柔軟なお客様対応を目指して

お客様からのお問い合わせ対応では、1ヶ月で何件のメールを処理されているのでしょうか。
遠藤さん:エンジニアやクリエイターといったプロ人材の方々から、少ないときで1日50件、多いときで100〜150件の問い合わせが発生しています。内容は、案件の問い合わせやサービス登録方法についてが多いですね。
まずはアシスタントの方に問い合わせメールを確認していただき、必要に応じて返信してもらうという業務フローです。特にエンジニアの方はビジネスのスピードや稼働状況の変化が速いため、リアルタイムで柔軟にご対応していくことが求められます。
お問合せ対応において、どういった点を重視されていますか。
遠藤さん:可能なら1時間以内に、どんなに遅くても1営業日中にはご返信することを目標に掲げています。また、お客様がどのような案件をお探しかをヒアリングするインタビューの満足度調査を送付しており、その結果もKPIの1つです。
メールのフィードバックに1日に1時間半。お客様対応の属人化にも課題を感じていた

以前はどのようなメールシステムを使用されていたのでしょうか。また、どのような課題があったのでしょうか。
遠藤さん:以前はGmailを使用し、アシスタントがお客様対応をしていました。どのメールに、どのように返信するかを社員からアシスタントに依頼する際には、Slack上でやり取りをしていました。
そのため、Slackを確認しながらGmailで返信することになり、アシスタントにとっては手間だったと思います。また、Gmailでは返信用のテンプレート文言をすべてのアシスタントのPCで一斉に変更できないため、何か変更があるたびにSlackで連絡をする必要があったことも課題に感じていました。
赤羽さん:まだお客様対応に慣れていないメンバーに対して、メール内容のフィードバックをする時間と手間が掛かっていました。メール画面を一緒に見ながら「この文面でよいですか」「この部分の表現を変えたほうがいい」といったコミュニケーションだけで5〜10分は使ってしまいます。ざっと計算してみても、1日1時間半くらいはメンバーへのフィードバックに時間を使っていたと思います。
アシスタントからはどのようなお悩みを聞いていましたか。
遠藤さん:アシスタントごとに業務が属人化することで、メール対応に差が出てしまうという悩みがありました。入社してすぐは共通のテンプレートを共有し、PCごとの設定の差が出ないようにするのですが、日々の業務を進めていく中で「秘伝のタレ」のようにアシスタント個人がカスタマイズしてしまい、少しずつ個人差が生まれてしまうのです。
コストやUI、ECシステムとの連携などの要素が、導入の決め手に
プロ人材向けのメールテンプレートは、どのくらいの頻度でアップデートしているのでしょうか。
遠藤さん:毎日変えているくらいの頻度ですね。例えば、FLEXYのサービスの伝え方を、職種ごとに変えたり、プロ人材とのインタビューを受けて微修正を加えたりと、日々アップデートしています。テンプレートを変更するときはSlackでアシスタントへ周知しているのですが、そのたびにコミュニケーションコストが発生してしまうので、ツール上で一括変更できればよいなと感じていました。
導入の決め手は分かりやすいUI。ツールの比較検討で重視した機能とは

Re:lationをお知りになったきっかけをお聞かせください。
赤羽さん:私の前職のEC事業でRe:lationを活用していたことがきっかけです。ECのお客様対応の場合、1つのメールアドレスを複数の担当者が共有し、組織としてお客様対応をすることになるため、かねてより組織内のコミュニケーションが円滑になるツールだと思っていました
ツールの選定では、どのような要素を重視されたのでしょうか。
赤羽さん:Re:lationを含め、3社で比較検討を進めました。その際に重視していた機能は2つです。
まず1つ目がテンプレート機能で禁止キーワードが設定できること。メール文面に禁止キーワードが残っていると、メール送信ができなくなる機能です。送信前に必ず修正しなければならない箇所がすぐに分かるようになっており、送信前の最終チェックを徹底させるためには必要だと考えました。
もう1つ重視していた機能が、操作ログ機能です。1つのGmailアカウントを複数名で共有すると、誰が設定を変更したのか、また誰がお客様へ返信したのか、分からなくなってしまいます。その結果、何かトラブルが起きたときに水掛け論となってしまい、最悪の場合は人間関係に溝が入ることもリスクとして想定できます。
Re:lationでは、システム利用者の操作内容を記録できるため、クレームが発生した場合は速やかに原因究明やお客様対応を行うことができます。
Re:lationに選定された決め手をお聞かせください。
赤羽さん:各種機能を含めた、Re:lationのUIです。担当者の振り分けや権限設定など、価格を考慮しても非常にリーズナブルだと思います。また、管理画面の余白とかフォントもシンプルで、一世代前のデザインのような他社ツールと比べても、初見で操作できるほど分かりやすいですね。
お客様対応の脱属人化を目指し、メールのテンプレート機能、承認依頼機能を活用

どのくらいの期間でRe:lationの運用が軌道に乗りましたか。
遠藤さん:チームへの導入は、1週間ほどで終わりました。すでに先行してRe:lationを導入していた他チームの方に操作を教えてもらいながら、アシスタントにもレクチャーしています。分かりやすいUIだったことで、アシスタントも1週間で操作には慣れました。先日も新しいアシスタントがRe:lationを使うようになったのですが、「何となく見ただけで分かります」と言っていましたね。
Re:lation導入後、特にどの機能を活用されてますか。
遠藤さん:メールのテンプレート機能ですね。具体的には、お客様のご案内フェーズ(初回挨拶、インタビュー実施済み、など)や業種、役職などに場合分けされており、129件のテンプレートを設定しています。
テンプレートの内容をアップデートする場合は、アシスタントや社員からSlackで意見をもらい、私が最終的に判断して更新しています。だいたい1週間に1件くらいの頻度でアップデートし続けることで、よりよいお客様対応を心がけています。
また、承認依頼の機能は新しいアシスタントさんが入社した際によく活用していますね。承認依頼は、新人のアシスタントがプロ人材のお客様にメールを送信する前に、上司の私の事前確認(承認)を挟むことができる機能です。
新人のアシスタントがお客様対応に慣れるにつれて活用頻度は減りますが、トラブルやクレーム案件の返信の場合には、必ず承認依頼を入れています。
お客様対応時間をチーム全体で月80時間も削減!メールの対応漏れもゼロに

Re:lationの導入で、どのような成果がありましたか。
赤羽さん:対象者に以前ヒアリングをした結果、自社システムとGmail、スプレッドシートでお客様対応をしていた頃と、Re:lationだけでお客様対応できている現在と比べて、1人あたり1時間/日を削減できていたことが分かりました。当時の担当者は4名だったので、チームで月間80時間も削減できた計算になります。
また、マネージャーが担当していた、依頼内容の抜け漏れのダブルチェック作業に掛かっていた1時間が、ほぼゼロになっています。20-30件に1件ほどの対応漏れが発生していましたが、これもゼロになりました。
Re:lationの導入で、チームにどのような変化がありましたか。
遠藤さん:担当者の心理的負担が低減されたことが大きな変化だと思います。以前は、Gmailに90件もお客様からの問い合わせが溜まっているのをみると、ゾッとする思いでした。しかし、Re:lationに未対応のメールが20件溜まっているのを見ても、不安に思うことはなく、むしろ安心できます。
アシスタント同士も同じ管理画面を見てお客様対応を進めているので、互いの認識に齟齬がなくなり、心理的な負担が減っていると聞きました。お客様対応をするには、とりあえずRe:lationだけを開けばすべて完結する、という状態は理想的です。
赤羽さん:テンプレート機能や承認依頼などを活用することで、アシスタント間のお客様対応のクオリティ差がなくなり、サービス品質が担保されるようになりました。お客様対応が脱・属人化できたのは、Re:lationのおかげだと思っています。
共有メールアドレスで対応する業務すべてに、Re:lationは活用できる

Re:lationはどのような企業におすすめできるでしょうか。
赤羽さん:共通メールアドレスで対応する業務は、すべてRe:lationで対応してもよいと思います。例えば「privacy@〇〇.co.jp」「info@〇〇.com」のようなメールアドレスです。IRやPR、ご相談窓口などを一元管理し、オペレーションを効率化することで、バックオフィスのコミュニケーションは非常にスムーズになるのではないでしょうか。
遠藤さん:toB、toC問わず、メールベースでお客様と多くのやり取りをする企業さんにはおすすめです。一定以上の企業規模になると、お客様対応件数が増えてしまい、どうしても抜け漏れが発生します。抜け漏れを防ぎながらもお客様対応のクオリティを向上させることができる、Re:lationはそんなツールですね。
今後の展望についてお聞かせください。
遠藤さん:FLEXYの目標は、ITフリーランス業界のトップリーダーとして日本企業のDXを先導するサービスになることです。エンジニアやクリエイター、技術顧問といったプロフェッショナルな方々にプロジェクト単位で案件をご紹介し、そしてプロ人材からの信頼を勝ち取り、「使い続けたいな」と思われるサービスを目指していきます。